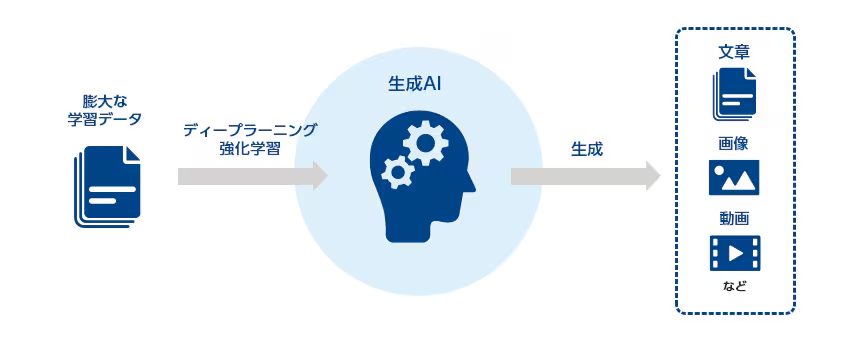DX推進が求められる中、多くの企業が「内製化」に注目していますが、エンジニア採用やチーム構築には高いハードルが伴います。
そこで注目すべきが、専属外部チームと共に開発を進める「ラボ型開発」という選択肢。知識やプロセスを自社に蓄積しながら、段階的に内製へ移行できる現実的なアプローチです。
本記事では、内製化に挑む企業がラボ開発を活用すべき理由と、仕組みを活かす戦略を解説します。
なぜ今企業は内製化を求め始めているのか
近年、企業がこぞって「開発の内製化」に注目するようになっています。背景には、外注に依存するだけでは解決できない課題や、持続的なデジタル競争力を企業内部に構築したいというニーズの高まりがあります。
特にDXの波が押し寄せる今、技術を「借りる」のではなく「育てる」姿勢が問われているのでしょう。
開発外注依存の限界とDX時代の組織ニーズ
これまで多くの企業は、システムやアプリケーションの開発を外注によって解決してきました。しかし、この方法にはいくつかの限界が浮かび上がっています。
- プロダクトやサービスに関する深い業務知識が外部にしか残らない
- 仕様変更のたびにコストと時間がかかり、柔軟な対応が難しい
- 内製化の視点がないため、組織に技術が蓄積されず“外注頼み”から脱却できない
こうした状況では、DXのスピードに組織が追いつけず、市場機会を逃すリスクが高まります。企業にとっての課題は「モノをつくること」ではなく、「価値を継続的に自社で生み出せる体制を持てるかどうか」に変わりつつあるのです。
技術を自社に残すことの戦略的価値
今後の企業競争において、技術力の外注はコストの問題ではなく、企業戦略そのものに関わる判断となっていきます。
- 業務システムやサービスに関する知識が社内に残らないと、改善や展開のスピードが鈍化
- 新たな施策やDXプロジェクトの立ち上げに毎回外注が必要となる
- プロダクト理解が乏しいまま、運用・保守が属人的・ブラックボックス化していく
そのため、技術を単なる「手段」ではなく、「組織が持つべき戦略資産」として位置づける視点が必要です。つまり、アウトプットではなく、ナレッジと再現性をいかに社内に残すかが問われているのです。
エンジニアを「資源」ではなく「競争力」と捉える時代へ
これまでは「人材確保=リソースの補充」という捉え方が一般的でした。
しかし今、企業に求められているのは、エンジニアを単なる作業者ではなく、事業成長のドライバーとして組織に組み込む視点です。
- プロダクトに深く関わることで、提案・改善ができるチームの存在
- 技術的判断が事業戦略に直結する組織文化の醸成
- 現場と開発が一体化し、スピードと柔軟性を持つ意思決定が可能になる体制
このように、エンジニアを「人的資源」ではなく「競争優位性の源泉」と捉える意識改革が、これからの組織づくりには欠かせません。外部に頼る開発から、自社で価値を生み出す体制への移行は、もはや選択肢ではなく戦略そのものになりつつあります。

「いきなり内製化」は危険?!段階的アプローチの必要性
内製化の重要性が高まる一方で、「とにかく自社だけでやろう」と急ぎすぎることは、大きなリスクを伴います。十分な準備や段階を踏まないままエンジニアを採用・育成し、開発体制を構築しようとすると、思ったように成果が出ず、むしろプロジェクトが停滞してしまう可能性があるからです。
成功する内製化には、段階的で現実的なアプローチが不可欠です。
まずは、外部の力を借りながら、自社に合った技術・知見・チーム文化を蓄積していく戦略が求められるでしょう。
採用・育成の負担と組織リスク
エンジニアを正社員として採用し、内製化チームを立ち上げるのは理想的に見えるかもしれませんが、現実には非常に高いハードルがあります。
- 優秀なエンジニアの採用競争が激化しており、そもそも確保が難しい
- 採用後すぐに即戦力として機能させることは困難で、教育・オンボーディングに時間とコストがかかる
- スキルのミスマッチや短期間での離職によって、組織が不安定になる可能性がある
このように、「いきなりの内製化」は、採用失敗や戦力不足によって開発力が逆に低下するというリスクを孕んでいます。内製化を急ぐあまり、継続的な成長や安定した開発体制の構築が二の次になるのは本末転倒でしょう。
属人性の排除と技術継承の仕組みづくり
内製化を進める上では、チーム内の「属人化」=特定の人に知識や技術が集中してしまうことが最大の課題の一つです。
属人化が進むと、その人物の退職や異動によってプロジェクト全体が崩れるリスクが高まります。
- 技術や設計思想を明文化する文化や体制が必要
- ドキュメント、レビュー、ペアプロ・モブプロといった継承の仕組みを設計段階から意識する
- 外部パートナーと協働する際も、技術移転を前提にした運用ルールを取り入れる
内製化とは「自社で開発できるようになること」だけではありません。継続的に開発スキルを保ち、他者に伝えられる仕組みを築くことこそが、真の内製化の鍵となります。
まずは“外部チームに学ばせる”という方法論
完全な内製体制を最初から構築するのではなく、「外部のプロフェッショナルチームから学ぶ」ことを出発点にするアプローチが注目されています。
- 外部の専属チームと継続的に協働し、自社業務の理解やプロセスを浸透させる
- 社内のメンバーがその開発スタイルや設計思想を観察・吸収できる環境を整える
- 開発フローやツールの使い方、ナレッジ管理方法まで「生きた教材」として活用できる
このように、ラボ型開発などの外部チームを活用することで、短期的には成果を出しつつ、長期的には自社に技術とノウハウを取り込むことが可能になるでしょう。リスクを抑えながら内製化へとつなげていく、非常に実践的かつ戦略的な選択肢です。

ラボ開発が内製化支援に向いている本質的な理由
「ラボ型開発」は単なる外注の手段ではなく、内製化に向けた移行フェーズとして極めて適したアプローチです。その本質は、「成果物の納品」を目的とした請負開発とは異なり、人とプロセスに長期的に投資する体制構築支援であるという点です。
特に専属チームによるナレッジの蓄積や、顧客主導による柔軟な開発体制が可能となるため、「外部に委託しながら自社に技術を残す」という難題を実現できます。
ここでは、内製化支援におけるラボ型開発の強みを見ていきましょう。
プロジェクトではなく「チーム」に投資する構造
従来の外注モデルでは、案件ごとに人員が変わり、納品後の関係性も断続的になることが一般的でした。しかしラボ開発では、「期間契約」ではなく「チーム契約」という考え方がベースにあります。
- 特定のプロジェクトだけでなく、継続的に関わるチームが組成される
- 業務理解・開発スタイル・プロダクト知識などがチームの中に時間をかけて蓄積される
- 単発の成果物ではなく、開発プロセス全体の改善にコミットする意識が共有される
つまり、“アウトソーシング”ではなく“チームビルディング”への投資と捉えることができ、これがそのまま内製化に向けた土台となっていきます。
専属メンバーによる業務知識の蓄積と継続性
ラボ型開発の最大の特徴のひとつが、同じメンバーが長期間にわたり、特定の企業・プロダクトに専属で関与することにあります。
内製化において極めて重要な「知識の蓄積と継承」の視点と強く結びつきます。
- 業務フローやプロダクト特性、社内文化に対する理解が深まり、言語化しづらい“暗黙知”も共有されやすくなる
- エンジニアが「仕様」だけでなく「業務背景」「ユーザー文脈」を理解した開発が可能になる
- 短期間での人員入れ替えがないため、チームの安定性・継続性が保たれる
その結果として、「言われたことを実装するだけ」の関係から、「一緒に事業をつくるパートナー」へと関係が進化します。こういったことこそが、内製化と最も近い体験です。
仕様変更や優先順位の柔軟なコントロールが可能
DXを推進する企業にとって、要件やビジネス環境の変化に即応できる開発体制は不可欠です。
ラボ型開発では、契約が「成果物」ではなく「工数(時間)」に基づいているため、仕様変更に柔軟に対応可能です。
- 要件定義の途中で優先順位が変わっても、追加見積や契約変更なしで対応できる
- 市場や顧客ニーズの変化を即座に反映させ、開発内容をリアルタイムに最適化できる
- ウォーターフォールでは難しかった“試行錯誤”や“仮説検証型の開発”も実施しやすい
このように、「変更ありき」の前提で開発できる柔軟性は、内製化を目指す企業にとって極めて重要です。自社の判断で優先順位をコントロールできるということは、開発体制を“自社戦略に従わせる”ことができるという意味でもあるでしょう。
顧客主導型の開発で、自社プロセスとの統合が進む
ラボ開発のもう一つの大きな価値は、「開発プロセスの主導権が自社にある」ことです。
つまり、外部パートナーでありながら、プロジェクトの設計・推進を自社のペースとルールで進めることが可能です。
- プロダクトオーナーやディレクターを自社で持ち、優先度や開発方針を主導できる
- チケット管理、スプリント設計、レビューサイクルなどを自社基準で運営し、開発プロセス全体を自社文化に沿わせられる
- 段階的に社内エンジニアや若手メンバーをチームに巻き込みながら、ナレッジ移転を進めることができる
このようにして、開発そのものを内製化するだけでなく、「自社の開発プロセス」を徐々に形成していくことができるのです。これは内製化を単なる採用・人材確保の問題ではなく、“組織能力をつくるプロセス”として捉えるうえで極めて本質的なステップといえるでしょう。

GeNEE-Vのラボ開発が“内製化の前段階”として有効な理由
多くの企業が内製化を志向するなかで、いきなり正社員エンジニアの採用やチーム構築に踏み切るのは、リスクが高く現実的ではありません。そうした課題に対し、GeNEE-Vのラボ型開発は“段階的な内製化”を実現するための極めて実践的なアプローチとして機能します。
最大の特長は、顧客専属の開発チームを月額制で提供し、期間中は顧客主導でプロジェクトを進行できる柔軟性にあります。請負契約とは異なり、要件や仕様変更に対して都度見積もりを必要とせず、まさに“内製に近い開発体験”を外部のプロ人材と共に実現できます。
また、GeNEE-Vでは、ブリッジSEを中心とした日本語対応チームが、要件定義やコミュニケーションの摩擦を最小化。そのため、顧客企業の業務知識やドメイン理解がチーム内に蓄積されやすく、開発だけでなくナレッジの移転が可能となります。結果として、将来的な内製チームの立ち上げやスピンアウトも視野に入れた運営ができるのです。
さらに、1名から始められる柔軟な契約形態は、スモールスタートから段階的にチームを拡大していく戦略とも相性が良く、失敗リスクを抑えながら「自社に合った開発組織」を模索することが可能です。
単なる外注ではなく、“継続性のある協働関係”と“知的資産の移管”を前提としたラボ開発。
GeNEE-Vはこの考え方を軸に、日本企業に対して開発支援以上の価値=技術の内製化支援パートナーとしてのポジションを確立しています。内製化を本気で目指す企業にとって、その一歩前の「学び、蓄積し、育てる」フェーズを支える存在として、非常に有効な選択肢です。

技術だけでなく“知的資産”を外部に蓄積・転移する視点
内製化を目指す企業にとって、単に技術を外部から得るだけでは不十分です。
重要なのは、その過程で得られるナレッジや業務理解といった“知的資産”を、いかに社内へ転移できるかという視点です。
ラボ型開発は、外部の専門チームと継続的に協働することで、コードや機能以上に価値ある「学習プロセス」や「意思決定の背景」までも取り込むことができる点において、極めて有効でしょう。
ナレッジの共有・継承を前提にしたチーム構築
ラボ型開発では、期間やプロジェクトごとに人員が入れ替わるのではなく、固定メンバーによる継続的な関与が前提となるため、自然と知識がチーム内に蓄積されやすい特徴があります。
- 業務知識やシステムの設計思想が共有されやすく、暗黙知もチーム内で自然に循環する
- チーム全体で学び合う環境が形成されることで、属人性を抑制しながらノウハウの継承が進む
- 社内メンバーが外部チームの開発手法や判断基準を“体験しながら学べる”構造が自然に成立する
このような環境下では、開発を「こなす」のではなく、共に理解し、成長する土壌が生まれやすくなります。これこそが、内製化に向けた「組織的学習」の第一歩と言えるでしょう。
ドキュメンテーションと業務理解を含めた資産化
知的資産は口頭でのやり取りや一時的な記憶だけでは定着しません。
知的資産を形式知として残す仕組み=ドキュメンテーションの文化が不可欠です。
- 設計意図や開発方針を含めた設計書・仕様書の体系化
- 業務プロセスと技術構造の関係を図示し、システムだけでなく業務全体への理解も促す
- 日々の議論や決定事項をナレッジベース化し、社内メンバーが検索・活用できる状態を維持する
重要なのは、「今の開発のため」ではなく「将来の再現性のため」に記録を残すという姿勢です。知的資産は、継続可能で再利用可能な形にして初めて価値を発揮するでしょう。
将来の内製チームへの「引き継ぎ」が前提となる開発運営
ラボ型開発を単なる外注やリソース補完と捉えるのではなく、あくまで「将来的に自社で運用・改善できるチームを立ち上げる準備段階」と位置づけることが重要です。
- 開発の各フェーズで「どの知識を誰にどう引き継ぐか」という観点を明確に持つ
- 日常的に使用するツールや開発フローにも、ドキュメント共有や学習用の導線を組み込む
- プロジェクト後半に慌てて“引き継ぎ資料”を作るのではなく、最初から「教える設計」で運営する
このように、「成果物の完成」ではなく「組織的な技術継承」をゴールに設定することで、ラボ型開発はただの開発手段から、内製化を見据えた“組織開発”の一部へと昇華します。

内製化の成功は「プロセス設計」から逆算すべき
多くの企業が内製化を「人を集めればできる」と誤解していますが、実際にはチームの構成や目標、運用ルールといった“プロセス設計”が内製化の成否を大きく左右します。
優秀な人材が揃っていても、目的や指針が曖昧であればチームは機能しません。逆に、明確な設計があれば、小さな体制でも着実に成果を積み上げることができます。
ここでは、内製化を成功に導くために必要なプロセス設計の観点を3つのポイントで整理しましょう。
成果物単位ではなく、運用と育成を前提にした設計が鍵
内製化とは、単に「自社でコードを書ける状態」にすることではなく、継続的に開発・改善・運用が回る体制を持つことです。
したがって、その設計は「何を作るか」ではなく、「どう回すか、どう育てるか」に重きを置くべきです。
- 初期段階から、運用フェーズにおける対応方法(バグ修正、仕様変更、顧客対応など)を見越して開発フローを組む
- 人の入れ替わりがあっても継続できるように、技術的判断の履歴やドキュメントの整備ルールを明文化
- 新人や異動者でもキャッチアップできる教育・引き継ぎの仕組みを予め想定した設計
このように、「完成させる」よりも「育てていく」ことを前提にした設計思想が、内製化の組織に持続力を与えます。
KPI・体制・責任分担を明確にする運用モデル
私がベトナムで開発チームと協働していたとき、最初に苦労したのが、プロジェクト全体における「誰が何を判断し、誰が何を管理するのか」が曖昧だったことです。エンジニアは動いているのに、成果がうまく積み上がらない。
そんな経験から痛感したのは、「KPI設計・役割設計・責任設計が整っていなければ、チームは迷子になる」ということです。
- KPI(達成目標)を、開発スピードやバグ件数だけでなく、「改善回数」や「ナレッジ共有数」などにも設定する
- プロダクトオーナー、開発リーダー、運用担当など、それぞれの意思決定範囲と責任範囲を明文化しておく
- 外部メンバーが関与する場合も、指示系統や承認プロセスを可視化し、業務の境界線を曖昧にしない
たとえば私が現地で改善に取り組んだときは、チームのSlackに「タスク起案 → 承認 → 実装 → テスト → リリース」のフローを可視化したワークフローを用意し、誰がどのフェーズをリードするかをチーム全体に定着させました。その結果、同じ体制のままでも判断と行動の速度が格段に上がり、リモートでも一体感のあるチーム運営ができるようになったのです。
内製化を進める上で、プロセスが属人的にならずに機能するためには、こうしたKPIと役割設計を先に決めておくことが不可欠です。チームに「自走力」を持たせるには、運用のルールを言語化し、共有し、継続的に見直す文化が求められるでしょう。
開発速度よりも“残る価値”を重視した体制構築
内製化では「早く作る」ことよりも、「長く使え、育てられる価値を残す」ことのほうが重要です。
スピードだけを追求すると、場当たり的な設計や技術的負債が蓄積し、結局将来の足を引っ張ることになります。
- 「このコードや機能は、1年後にもメンテナンスできるか?」という視点で設計・実装を評価
- 開発の中で生まれる判断や知見を、共有資料や定例レビューに蓄積し続ける習慣をつくる
- 新技術の導入やツール選定も、「将来のメンテナンス性」「他のメンバーへの引き継ぎやすさ」を基準に判断する
内製化は一度作って終わりではありません。時間が経つほど価値が増す“仕組み”として体制を設計することが、持続可能な開発組織を生む基盤になります。最初からその視点でチームを作れるかどうかが、内製化の成否を決定づけるでしょう。

外部委託と内製の“中間領域”にこそ最適解がある
外部への丸投げではなく、自社で価値を生み出すための力を育てる──それが今、企業に求められている開発体制の本質です。
ラボ型開発は、単なるリソース補完の手段ではなく、知識と技術を自社に蓄積し、組織として自走できる状態をつくる“架け橋*として大きな可能性を秘めています。
「いきなりの内製化」は難しくても、段階を踏みながら正しいパートナーと共に成長することは十分に現実的です。いまこの瞬間から、“成果物”ではなく“未来に残る力”に投資する視点を持つことが、持続可能なDXと競争力ある組織づくりへの第一歩になるはずです。